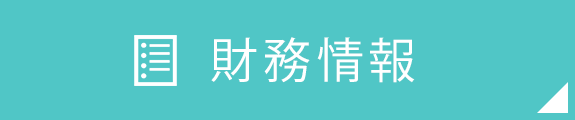介護施設における法的問題Q&A
施設の運営上生じる様々な法的問題について、当園元顧問弁護士のの櫻井康夫先生に分かりやすく解説していただきます。
櫻井康夫先生の略歴
1971年横浜地方裁判所判事補となる。以後、東京、横浜、水戸、静岡にて、主に家庭裁判所判事として2003年まで勤務。2014年まで静岡にて公証人。同年5月、静岡県弁護士会に弁護士登録、2020年2月弁護士登録抹消。
質問一覧
▼質問を選択すると対応するQ&Aに移動することができます。
【Q1】後見人が、本人に代わって医療行為の同意をすることはできますか。
(回答)できません。
(1)本来、医療行為は、それを受ける患者本人自身の身体と命にかかわることですので、それを受けるか、否かは本人だけが決められる「一身専属的」なものであり、自己決定権の内容に属するのであって、親族であっても本人に判断能力がある場合には、他の者が代わって同意することはできません。しかし、本人が意識不明や明確な判断ができないような場合には、親族の同意で足りるというのが、医療機関の実務のようです。
(2)後見人の職務範囲は、本人の財産を管理することと、身上を監護することです。この問題は、身上監護に関することですので、身上監護について述べることとします。身上監護とは、本人を見守り、本人の心身の状況を常日頃から把握し(家族やヘルパーなどの介護関係者らから、間接的にでもいいですが)、必要に応じて、ケアマネジャーらと連携し、介護契約を締結し、どの程度の介護を受けるかを決めることや、適切な病院を探して、その病院に行かせて診察を受けさせたり、時には入院させ、治療を受けさせたりする医療契約又は介護契約を、本人を代理して締結することです。これには費用がかかるので、本人の財産から後見人が支払いますが、このように財産管理とも関係してきます。なお、後見人の職務範囲には、本人を直接介護することの事実行為は含まれません。
(3)問題となるのは、本人が、特に侵襲的な医療行為(検査を含む。検査といっても、時には危険を伴うこともあり、病院はほとんど本人に同意書を求めます。)を受ける際に、本人が認知症などで、あるいは、突然の病気により意識がないような時には、本人から同意が取れない場合があります。しかも、緊急な治療が必要です。しかし、本人にとっても、医療機関にしても、同意が取れないからといって、何らの措置もせずに放置しておくわけにもいきません。
(4)このような場合には、親族(多くの高齢者の場合では、原則として、まず、配偶者が、次いで同居の子、子、兄弟姉妹、甥姪の順になります。)がいれば、なるべく近い親族(内縁の配偶者には、同意の権限は、原則として、ありません。)に同意をしてもらうことになるでしょう。
昨今、親族と疎遠だったり、所在が分からない場合も多くなってきました。このような場合には、同意をする者がいないことになります。医療機関は、このような場合には、後見人に同意を求めてくることもあるようです。医療機関は、後見人に同意権限があるものと考えていて、現に、医療機関から同意を求められたという経験をした後見人は、相当数あるようです。しかし、後見人には同意をする権限はありませんので、すべきではありません。そもそも、後見人が財産管理を主たる目的とする場合には、親族ではない弁護士などの専門職が後見人に選ばれますが、このような者に、本人の生命を左右しかねないような判断の権限を与えることは、適切ではありません。
ただし、採血、軽い怪我の治療や肺炎や風邪の予防注射などは、本来の後見人の身上監護の権限の行使としてなされた診療契約に含まれるものとして、その都度の同意は不要と考えられますが、医療機関は、確実を期するために、後見人が同意という形で、確認することもあるでしょう。
【Q2】入所者の治療に関し、施設長が医療機関から医療行為の同意を求められた場合、これに応じなければなりませんか。
(回答)応じるべきではありません。
(1)質問1で説明したように、本来、治療行為に同意するか否かは、本人の自己決定権の問題ですから、介護施設の施設長は、これに同意することはできません。
しかし、施設長に同意を求めてくるのは、本人の親族がいないか、親族に同意を求められない事情がある場合でしょう。施設長は、本人と常日頃、長い間接しているので、医療機関としては、親族に準じた者と考え、施設長に対して、入所者の手術等について同意を求めてくることも、現実にあるようです。
施設は介護することを契約上の義務として負ってはいますが、入所者の生命・身体に関わる医療行為に同意を与えることまでの義務があるわけではありませんから、当然、医療機関の求めに応じることはできませんし、してはなりません。
(2)ただし、施設長は、本人について、入所時に、あるいはその後に、本人の平生の、あるいは終末期の医療についての希望を書面で聞き取っていたり、また、それがなくとも、普段の本人の言動から本人が望んでいたこと等の情報を持っているので、本人の利益のためにも、それを医療機関に伝えて、医療機関が適切な措置をとれるように協力することは、差支えありませんし、むしろ望ましいことです。
【Q3】施設入所にあたり、後見人に対し保証人や身元引受人になることを求めることはできますか。
(回答)できません。
(1)後見人の職務については、質問1で説明したとおりですので、参照してください。
まず、「保証人」のことですが、施設としては、本人に資力がなく、入所費用等の支払いがない場合に、本人に代わって、費用を支払う責任を負うことを、施設に対して約束した者です。これは、書面でしなければなりません。施設としても、費用を支払ってもらえないことは、施設の事業の運営に大きな支障をきたすので、保証人をつけることを要求するのは、当然のことです。
(2)しかし、後見人が本人の保証人になることはできません。その理由は、もし、後見人が本人に代わって介護費用を支払った場合には、本人に求償することができますが、これでは、後見人と本人とが利益相反関係になってしまいますので、その意味で保証人になることができないのです。普通は、親族等が保証人(医療機関では、多くの場合、別世帯の資力のある者を要求することがあるので、配偶者は、保証人になれない場合があります。)になっています。
(3)保証人がどうしても確保できない場合、保証人の役割を果たしてくれる法人も現れ始めているようですから、後見人としては、そのような法人を探して、その法人の業務内容を精査し、施設とも相談して、そのような法人が保証人になれるか、よく検討してください。
(4)身元引受人(身元保証人という場合もあります。以下、併せて「身元引受人」といいます。)ですが、まず、本人の「身元」を引き受ける責任を負うことになります。本人が、何らかの事情で退所する場合に本人の所有物を引き取ること、死亡した場合には、遺体や遺品を引き取ることでしょう。施設として、入所の際に身元引受人を要求することは、合理的な必要性があります。
しかし、身元引受人は、本人の身元を引き受ける責任に加えて、保証人のように、費用を立て替えて支払う責任を負う場合があります。そのため、契約書において、身元引受人がどのような義務を負うとされているかをよく確認する必要があります。
なお、退所の場合には、後見人は、身上監護の職務として、自宅介護にするか、新たな介護施設を探して入所させるかを、決めなければなりません。
(5)しかし、身元引受人がどうしてもいない場合には、身元引受人と同様な責任を負ってくれる法人も多少は現れ始めているようなので、後見人としては、保証人の場合と同様に、適切なそのような法人を探し、施設と相談してください。
【Q4】後見人の職務である身上監護と財産管理に優先順位はありますか。
(回答)優先順位はありません。
(1)民法の規定では、身上監護の義務が財産管理義務よりも先に規定されていますが、これは優先関係を示したものではありません。むしろ、双方が相まって、後見人の職務が、よりよく全うされることになります。
(2)身上監護の義務とは、常日頃から本人を見守り、本人の意思を尊重しつつ、心身の状態や日常の生活に配慮し、本人の心身の状況にあわせて、適切な措置を講じることです。病気になったら、治療を受けさせたり、入院させたり(そのために、適切な医療機関を把握しておく必要があります。)、生活が一人では覚束なくなったときには、必要な介護を受けさせるようにし、治療や介護が適切になされているかを見守ることです。また、ケアマネジャー等の福祉関係者と相談し、介護度が高くなった場合には、時には居住していた不動産を売却して(これには、家庭裁判所の許可が必要です。)、適切な有料老人ホームなどに入所させることなども含まれます。これらの後見人の仕事は、とても骨の折れる時間のかかる仕事です。そして、これらの費用は、後見人が管理している本人の財産から支払うことになります。
居住の不動産を処分し、施設に入所させることもあることは、身上監護と財産管理とが密接に結びついていることが分かります。
(3)財産管理の義務は、判断能力の衰えにより、本人が適切に自分の財産を管理できなくなった場合に、その義務を果たすために選任されるものですから、後見人は、本人の身上を配慮しつつ、その財産を管理し、時には処分することもできます。後見人は、特別な預金口座を作って、一括管理し、年金の支払いを受けたり、本人にかかわる諸費用を支払い、時には本人が所有するアパートなどの不動産の管理もします。多額の預金がある場合には、家庭裁判所の指示によって、当面必要な金額を除いて信託銀行に預託させることもあります。
財産が多額な場合、家庭裁判所は、法律の専門職の弁護士等を後見人に選任していますが、これらの専門職は、必ずしも福祉に通暁しているとはいえないため、ややもすれば、身上監護の面が手薄になると聞きます。そのような場合には、福祉関係者を複数後見人の一人に加え、身上監護については、その後見人が担当するということもあり得るでしょう。
【Q5】要介護度3以上であれば、成年後見の対象になりますか。
(回答)場合によります。
(1)成年後見には、判断能力の程度に従って、軽い順序から「補助」(これは、判断能力はあるが、本人の安全のために補助人が付けられるもので、申立て自体に本人の同意が必要です。)、「保佐」、それに「後見」がありますが、ここでは、後見だけを述べることとします。
(2)要介護度3について、その状態像は、身体的な側面と精神的な側面があります。法定後見の対象となるか否かは、精神的な側面のみをとらえてこれを行います。「精神的な」ということは、判断能力のことで、結局は、自分の財産を適切に管理しあるいは処分できるかということになります。
(3)身体的な病気や事故による怪我による全身麻痺により、常に全面的な介護が必要な場合でも、判断能力が損なわれていなければ、後見の対象にはなりません。しかし、多くの場合、高齢になって日常生活に介護が必要になる方は、認知症も進んで判断能力が衰えていることも多いことがよくあることです。
要介護度3の状態像の大まかなことをいくつか挙げると次のとおりです。すなわち、「いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。」、あるいは「毎日の日課、自分の生年月日を言うことができない又は分からなくなる、ついさっきまで何をしていたのか分からないといったような物忘れの症状が現れ、また、周囲のことに気が配れなくなる。」、「昼夜逆転、暴力行為、大声や奇声をあげる、介護の拒絶などの行動が現れることがある。」とされますが、多くの事例では、このような状態では、すべての状態が重なっていなくとも、自分の財産を適切に管理していくことは、かなり困難であり、容易に財産をだまし取られるような危険もあるので、多くの場合には、後見の対象となる可能性が高いでしょう。
【Q6】利用契約書の本人欄について、本人に代わり家族に署名してもらうことは、問題はありますか。
(回答)問題はありません。
(1)このようなことを、署名の「代行」と言います。署名は、本来、本人が自らすることを、当然に含んでいるのですが、例外的に本人には判断能力があるが、手が不自由で、自分で署名できないような場合には、本人の指示や依頼を受けて、他人が本人の代わりに、契約書に本人の名前を書くことは、差支えありません。本人が署名したものとして契約は有効に成立します。ただし、本人に判断能力がないときには、本人の許諾なくして勝手に本人の名前を署名してしまうことになり、契約の効果は生じないことになるので、注意してください。
(2)本来は、本人が自ら署名すべきことなのですから、このように例外的な場合には、なぜ他人が本人の名前を署名したか、その理由を明確かつ具体的に附記しておくべきです(施設入所契約書には、署名代行者欄があるものもあります。)。
例えば、「本人○○は、この契約内容をよく理解しているが、○○○(病名等)により、手が不自由なため、自ら署名できないので本人の依頼により、私・長男□▽が母に代わって署名した。」として、長男が、入所契約者本人としての母の名前を書き、次いで長男の氏名・捺印・住所を記載します。
【Q7】特別養護老人ホームに入所中の方が、体調不良であっても治療を受けることを拒んでいます。判断能力を欠く常況にはありませんが、今後、体調が急変することも考えられます。施設としてはどのように対応したらよいでしょうか。
(回答)本人や親族と、時には医療者も交えて、よく話し合って対応するしかありません。状況によっては、本人の希望どおりに、治療を受けないという意向を尊重してよい場合もあるでしょう。
(1)本人の生き方、死に方も含めて、どのようにするかは、本来、本人が決めることであって、自己の意思に反して他から生き方や死に方を強制されることはありません、ということはできます。しかし、これは生命倫理にかかわる微妙で困難な問題です。インフォームド・コンセントが強調され、患者の自己決定権がより鮮明に意識される昨今、検査や医療を拒否する方々が増えてきたというのが医療機関の認識です。
(2)本人に判断能力があるといっても、年齢、心身の状態を踏まえ、なぜ治療を拒むのかなどを、時期をたがえて複数回、よく聞き取り理解することが、まず必要です。
特別養護老人ホームの入所者は、通常は、高齢で要介護度3以上ですから、判断能力(この場合の判断能力は、財産管理に関する能力より低くても尊重する必要があります。)があるといっても、やや低下しているのが実情でしょうから、本人の意向だからといっても鵜呑みにせず、その意向を慎重に見極める必要があります。
(3)本人がなぜ治療を拒否するのか、その理由は人さまざまでしょうが、しっかりした納得できる理由がないと思われる時には、本人に対し、今後起こり得る病状、それに対する治療の必要性(その内容、期間、効果、副作用、苦痛の有無、費用等)を分かりやすく説明し、親族を交えて、治療を受けることを、できれば医師も加わって、懇切に説得するべきでしょう。
今現在、苦痛もないと、医学的には病気があっても、それ以上の治療を受けないでもかまわないと容易に思うかもしれません。しかし、いざ耐え難い痛みなどの苦痛がおきれば、その苦痛を取り去るだけの治療を受けることを拒む方は、ほとんどいないのではないでしょうか。そのような苦痛を経験し、治療により苦痛がなくなれば、さらにもっと根本的な治療を受け入れるかもしれません。人の考えは、容易に変わることもあるのです。とくに、終末期の場合には、身体の状況も刻々と変化し、それに応じて、本人や家族の考えは、変転するものです。一旦、治療を拒絶したからといって、いつまでもそうであるとは限りませんので、常に本人の意向の確認が必要です。
(4)しかし、精神的に、判断能力がほぼ完全であり、諸般の事情から、現在も、将来も苦痛がないか、小さい場合に、もはや、いかなる場合でも、治療を受けないことの結果を熟知しながらも、強固に治療を受けないという方もおられるでしょう。
このような場合でも、本人の意向は、家族に対する気兼ね、経済的な負担、今後の回復の希望のないことによる生きることへの疲れや絶望感などさまざまでしょうから、本人や家族の意向を再度よく聴きながら、どこまでが真意なのかを的確につきとめ、場合によっては、その懸念を取り除く方法もあることも含めて、さらに説得することもあり得るでしょう。
それでもなお、本人の意向が確固たるものである場合には、それ以上を強制することはできないとして、施設としては、医療機関とも相談のうえ、医療機関に対して、治療を求めないこと、治療を継続しないことも許されることもあるでしょう。
(5)いずれにしても、このようなことに関与する場合には、後日、そのような措置が適切であったか否かを検証するためにも、また、遺族との紛争を避けるためにも、施設関係者、医師、できれば第三者も含め、複数の者で検討して決めるべきであり、その経過は、逐一詳細に記録にとどめておく必要があります。本人との対話をすべて録音、録画しておくことも、考慮すべきです。本人から、治療を受けることの拒否の意向と、施設関係者や医師に対する免責の書面を作成しておいてもらうことも一つの方法です。
【Q8】高齢者の施設で働く者に、インフルエンザの予防接種を義務付けることはできますか。また、就業規則に定めたら義務付けが可能ですか。
(回答)いずれにしても、義務付けることはできません。
(1)高齢である入所者(以下「入所者」といいます。)を預かる特別養護老人ホームなど高齢者を介護する施設においては、高齢者を介護する者(介護士、看護師、それらの補助者、以下「職員」といいます。)が、インフルエンザに感染したとき、発症が明らかになる前でも、または、罹患した職員がそれを意に介せずに仕事をしていると、高齢者に感染させてしまい、高齢者を危険な事態に至らしめることは明らかです。
高齢者は、食事も少なくなり、低栄養になりがちで、加齢による免疫力の低下など基礎体力が低下し、また、複数の疾患を持っていることが多いのでインフルエンザに感染しやすく、感染した場合には、気管支炎、肺炎などの重篤な症状をきたし、ときには、死亡に至る危険があり得ます。インフルエンザは、普通の風邪と違って、高熱、頭痛、関節痛などの重篤な症状が起きやすく、咳やくしゃみで、周囲の者に感染する危険等が大きいのが特徴です。
(2)これらの施設には、高齢の入所者を預かり、心身の健康を維持し、快適に過ごせるように努める義務(安全配慮義務)があります。その一環として、施設で働く者がインフルエンザに罹患し、それを入所者に感染させ、時には命の危険にさらすことは、安全配慮義務を負う施設としては、決してあってはならないことです。
(3)そこで、施設の管理者としては、常に職員の健康に気を付け、感染性の病気(ここでは、以下インフルエンザについて述べることとします。)に罹患しているか否かを注意深く観察し、もし、そのような兆候が分かれば、その者を休業させる義務があり、業務命令として、休ませることができます。しかし、インフルエンザでも、潜伏期間があって、発症するまでは、また発症直後では、普段の健康状態と変わらず、その兆候をすべての従業員ついて的確にとらえることは困難です。しかし、そのような期間でも、他人に感染させる危険があります。
(4)そこで、施設としては、事前にできる限り、インフルエンザの発症、感染を防ぐために、職員に対してその予防接種を勧めたいところですし、それはたいへん望ましいことです。そこで、できれば職員全員(事務、厨房で調理をする者など、高齢者に直接接する機会の少ない者も含め)に対して、少なくとも介護に直接かかわる者に対して、あらかじめ予防接種を受けさせたいところです。
(5)しかし、予防接種法や厚労省の通達によれば、予防接種法の対象となる疾病を予防すべき者でも、接種を受けるか否かは、本人の同意を要するとなっています。つまり、現行の法の規定では、予防接種の実施主体である市町村等については、一定の接種対象者に対して、接種を受けることを勧奨するものとし、また、その対象者は、接種を受けることに努めなければならないとして、いわゆる「努力義務」になっています。したがって、接種の対象者にもなっていない職員に対しては、強制的に接種をすること、つまり、業務命令によって義務付けることはできず、接種を受けるか否かは、全くの職員の「任意」にゆだねられています。
(6)次に、就業規則に定めれば、職員の接種を義務付けることができるか否かですが、これをもってしても、接種の義務付けることはできません。就業規則は、労働基準法により、「就業規則は、法令・・に反してはならない。」とあること及び予防接種法では、単に「努力義務」にとどめていることの趣旨を踏まえれば、就業規則で強制的に接種させることを定めても、無効といわねばなりません。なお、一定の条件をつけて就業規則に定めれば、義務付けることができるとの考えもあるようですが、大勢は、否定的ですし、そのような解釈には無理があるといわねばなりません。
(7)しかし、施設としては、高齢者の入所者を預かっている責任上、可能な限り、すべての職員に、インフルエンザの予防接種を受けてもらうよう努力するとともに、高齢者施設で働く者としても、特別の理由のない限り、道義的な義務があるといっても差し支えないといってもいいのではないでしょうか。施設としては、職員に対し、予防接種の意義、有効性、副反応をよく説明し(できれば、嘱託医などの医師からの説明)、十分理解を得た上で、同意の上、任意に接種をしてもらうように働きかけ、可能な限り、すべての職員が予防接種を受けることが、望ましいやり方です。ただし、その際、強制になりかねないように注意しなければなりません。さらに、接種費用も施設で負担することが望ましいでしょう。施設内で行う場合には、接種後に現れることもある副反応に、嘱託医が即応できる態勢をとっておくことも必要です。
(8)なお、入所者(ほとんどの方が、予防接種法の対象になるでしょう。)のインフルエンザの予防接種は、入所者の意思に基づき、その責任においてなされるもので、その意思確認を行わず、一律に接種することはあってはならないことです。接種にあたっては、嘱託医などと相談の上、その意義、有効性、副反応の可能性を十分説明し、入所者の意思確認ができないか、困難なときには、家族、嘱託医などの協力を得ながら、可能な限りその意思確認(家族により、その意思が推定される場合も含む。)に努め、確認できた場合のみ接種すべきでしょう。
【Q9】介護施設における介護事故の事業者の民事的な法的責任とはどのようなものですか。
(回答)ここでは、介護事故の法的責任の総論的な法律論が書かれています。この総論的な法律論は、分かりづらいかもしれませんので、後のQ10の転倒(ここでは落下事故も含みます。以下「転倒」といいます。)及びQ11の誤嚥事故の具体的な事例を先にお読みいただいてから、この箇所をお読みいただいてもけっこうです。
第1_介護事業者の介護事故にかかわる法的責任
(1)ここでは、特別養護老人ホーム等における介護に関する事故(以下「事故」といいます。)について、入居して介護する際の事故、その他ショートステイとデイケアにかかわる施設内部での事故について扱います。事故はその他、利用者の送迎、無断外出による事故等の施設外部で起きる事故もありますが、ここでは、とりあげません。しかし、基本的な考え方は、他の事故においても同じでことです。
また、この事故は、さまざまな事故がありますが、さらに絞って介護事業者が介護をするにあたって、利用者に起きた転倒、誤嚥事故について言及します。
(2)介護事業者は、一定の物的設備の存否・機能、職員の資格・人員などの要件を満たしているかを知事・市長の認定を受けた上で事業を営むことができる高度に専門的な事業です。また、その事業の性格上、利用者の命に係わるような事態にも適切に対処し、入所して日々の生活を送る上で、利用者の利益を最大限図るように努める義務があります。
(3)以上の次第で、事業者は、利用者の心身の状況にあわせて、その専門知識や経験を活かし、適切な介護をしなければなりません。介護福祉士(以下「介護士」という。)は、介護の専門家としての専門知識があり、それが国家資格で保証もされています。介護士は専門家としての、補助者もそれに準じた責任があり、それは、利用者本人やその家族のみならず、社会一般からも期待されているところです。
特に、利用者の身体生命の安全を守ることは、施設の重要な義務であり、これは入所契約によって生じる「安全配慮義務」といわれています。この義務に違反して起きたと認められる事故については、施設は、利用者に生じた有形無形の損害を賠償する責任が生じます。これらの注意義務は、「介護の実践における介護水準に照らし要求される注意義務を怠った場合」といえます。単に、職員の配置人数が適法であって、かつ、標準的な介護マニュアルに従っていたというだけでは、この義務を果たしたとはいえません。
また、職員が急に辞めてしまった様な場合にも、即座にできる得る限りの即応対策を講じなければなりません。
なお、「不法行為責任」も生じることがありますが、争点は、ほぼ同じことなので、契約上の「安全配慮義務」違反による責任について述べることとします。
(4)安全配慮義務の違反があるとして責任が認められる要件
ア_施設に安全配慮義務の違反(注意義務違反)があったとされるためには、「過失があること」、「事故とその過失に相当因果関係」(常識的に考えて、過失とみられる職員の作為・不作為が、発生した事故と関連しているということです。)あったことです。
イ_まず、「安全配慮義務違反があった」すなわち過失があったとされるには、以下の要件が必要です。
①_その事故の起きる危険性について、予見可能であり、予見すべきであったといえることです。つまり、職員がある介護行為をする、あるいはしなかったことによって、事故が発生するかもしれないとの認識があったか、あるいは、もっと注意・配慮していれば、事故の発生を認識することができたということ。
②_次いで、要求される程度の相応・適切な措置をとっていれば、事故は防げたであろうといえる、ということです。しかし、いかにその施設として、万全の取り得る措置をとっていたとしても、どうしても防げなかったと認められるような事故について、施設は責任を問われることはありませんが、実際事故が起きてしまったときに、事故が不可抗力であったと認められる事例は、転倒についていえば、必ずしも多くはありません。
③_事故防止については、いろいろな参考になる書籍も多く、そのよう本を施設に備えおいて、職員に読ませ(時には輪読会をするなど)、常日頃から、具体的に事故防止の意識を高め、かつ、事故になりかねないような事態を多く把握・記録して、それに対して、単なる精神論ではなく、具体的に考え得る防止措置を、限られた人的資源ではありますが、最大限有効に活用して、職員全員で検討し、問題意識を共有し、積み重ねて行くことが大切です。事故こそ起きなかったけれども、危険であった事例について、具体的な事例検討会を適宜開くことも、有効です。
④_訴訟において、これらの判断にあたっては、いろいろな要素が検討されますが、とくに日々の介護日誌、各種の医療記録、家族から要望書、介護の記録、本人の心身の状態を記載した書面、入所時あるいはその後の家族との遣り取りの記録等の客観的な資料や記録が重要な証拠となります。それゆえ、ふだんからこまめに、各種の記録を作成し、保管しておくことも大切です。
ウ_相当因果関係とは、施設内での転倒によって、そのけがや骨折が起きたと認められることです。転倒骨折して入院後に肺炎で死亡した場合に、骨折と肺炎には、通常起こり得る関連があるとは必ずしもいえませんので、特段の事情がない限り、相当因果関係はないとされるでしょう。また、救急車で、けがをした入所者を病院に搬送中に、救急車が事故を起こして、利用者が新たな骨折をしたり、死亡したとか、病院内で多剤耐性菌に感染して死亡した場合にも、施設は死亡についてまでは、責任を負うことはありません。
(5)損害賠償額
施設に事故の責任が認められた場合の負うべき損害の内容は、およその次のとおりです。なお、家族と金額の示談交渉をする場合には、保険会社と相談しながら、あるいは、代行、同席してもらい、または、弁護士に相談、あるいは委任して進めるのがいいでしょう。
ア_積極損害
けがを負った場合の入院・通院の治療費用(診察料、検査料、入院料、入院中の食費、症状固定までの間、ただし、健康保険などを利用した場合には、実際に負担した金額)、入院に伴う洗面具等の諸雑費、入院中の食費、治療の必要性から特別な部屋(個室など)を利用した場合の差額料、家族の介護費用又は付き添い看護料、交通費など。死亡事故の場合には、死亡に至るまでに要した治療費、その他は、死亡に至るまでの間支出した費用は、けがのときと同様です。
イ_逸出利益の損害
高齢者の場合、稼働していないことが多いので、休業補償的な損害はないことが多いでしょう。死亡事故では、生きていたならば、受給できた年金の平均余命までの金額。ただし、年金が遺族年金の場合は、相続の対象となりませんので、損害にはなりません。
ウ_慰謝料
けがの場合は、入院や通院期間に応じて、交通事故による慰謝料の算定表を参考に決められることになるでしょう。後遺症の慰謝料も、同様です。
死亡の場合には、これがいちばん高額になるのですが、本人慰謝料のほか家族の慰謝料も含むのか、内縁の妻かなど、その他いろいろな事情が考慮されますので、一概にはいえませんが、介護についての過失が死亡と因果関係があるとされた事例では、1,500万円から2,000万円前後とされた事例が多くみられます。
(6)判例は、一般的に専門性のある多くの職業について、「高度の注意義務」を要求する傾向にあります。介護に携わる事業者、職員にも当然「高度の注意義務」が要求されています。介護関係者から見ると、過酷ではないかと思われるほどの注意義務を課する判決もありますが、このような判例の傾向は確定していますので、関係者は、その旨心して、利用者に対してできる限り適切な介護をしなければなりません。
第2_事故後の対応など
(1)いずれの事故にも通じることですが、事故が起こった後の対応が大切です。まず、事故の内容を、職員などから聞き取って、冷静かつ、事実を正確に把握し、早期に書面にしておくことです。次いで、窓口を1本にして、家族には可能な限り早期に、かつ、事故の事実関係のすべてを正直に正確に知らせるべきです。また、家族からの質問に対しても、誠実に事実を伝えることです。施設が何か隠しているのではとの疑惑を家族が抱きかねない言動は、もっとも避けるべきことです。
また、事故が起きた際、施設でとり得る措置は、可能な限り速やかに行なわなければならなりません。とくに誤嚥事故では、一刻も早く取るべき措置を取らねばなりません。例えば、速やかに救急車を呼ぶ、その間の誰でもできる回復措置、あるいは蘇生措置をとることです。とくに誤嚥事故では、普段から、医師、看護師から医療措置ではない簡単な救命措置方法の習っておき、誰でも直ちにそれができるように、常に実地訓練をしておくことが肝要です。
(2)また、転倒事故では、本人の訴え(高齢者は、重い骨折でも痛みをあまり訴えないこともままあるものです。)を注意深く聞いて、速やかに嘱託医の診察を仰ぎながら、即座に施設で救急車を呼ぶなり、嘱託医と家族の意見も聴きながら、施設の車あるいは家族の車で(この際には、できれば職員も付き添う。)適切な病院に搬送することです。後掲の転倒事故事例3は、実際よりも事態を軽く見て、事故後半日たって、家族に病院搬送させ、医師の診断では骨折の程度も重かったということで、感情を害したと思われる事例です。
(3)誤嚥事故については、特別養護老人ホ-ムに入所していた高齢者が、カマボコ片等を誤嚥し、低酸素状態に陥り、その後死亡した事例で、誤嚥と死亡については、施設の責任を否定しましたが、職員が誤嚥に対する処置をした結果、入所者の状態が安定したと判断し、ただちに救急車を呼ばずにいたところ、容体が急変し、救急車を呼んだが、間に合わずに死亡したという事例で、いったん応急措置をしたとしても、気道内の異物が完全に除去されたと的確に判断できないのであるから、ただちに救急車を呼ぶなり、嘱託医の診察を仰ぐきだったとして、死亡そのものではなく、「死期を早めた責任」を認めた事例があります。
(4)なお、家族から「謝罪」を求められることもあるようですが、「謝罪」したからといって、それだけで、法的な責任までも認めたこととは、必ずしも評価されません。状況にもよるでしょうが、まず、事故が起きてしまったことについて、本人や家族に対して謝罪(具体的な対応や言葉使いは難しいときもありましょうが)をするということもあり得るでしょう。
(5)すべての事故について言えることですが、訴訟に至らず話し合いで解決される事例も多く、訴訟に至った事例では、ふだんから利用者側と施設に信頼関係が築かれていなかったり、施設に事故後の家族に対する対応が適切でなかったことが、こじれる原因になっている場合も多いと推察されるので、事故後の適切、迅速な対応が望まれます。また、当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話が余計こじれることがままありますので、弁護士などの専門家の意見をあらかじめ聞いて交渉するか、場合によっては、示談交渉を弁護士に委任することも考えられるでしょう。訴訟になると、施設側も、費用や精神的な負担は大きく、利用者に対する日々の介護業務にも悪影響を及ぼしかねません。当然のことですが、常日頃から懇切丁寧に介護にあたり、入所者とその家族との信頼関係を築いておくことが、もっとも大切です。
(6)特別養護老人ホームなどの施設で働く職員にとって、介護の仕事は、地味で忍耐を要する仕事であって、夜勤や休日出勤もあり、その心身への負担はたいへん大きなものがあります。また、その待遇についても、諸般の事情により、必ずしも満足とは言いかねる状態にあるようです。このような状況の中で日夜苦労されている職員に対し、施設の管理者としては、その心身の状態をきめ細かく把握し、適正な公平な労働条件等が満たされているか、職員同士、管理者との間に和が保たれているかなどについて、常に細心の配慮をすることが、介護事故を防ぐ大前提であることは、言うまでもありません。
第3_損害保険の必要
社会福祉法人は、一般的にその財務基盤が弱い傾向にありますから、多額の損害賠償金を支払うことは、施設の諸般の運営に困難をきたす危険があり、他の入所者の介護に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。このような事態を避けるためにも、損害を補償される(どの範囲までが補償の対象となるかをよく確認すること)保険に加入することは、不可欠です。なお、以前は、無断外出にともなう、物的でない損害に対しては、保険の適用がありませんでしたが、現在では、これを対象に含む保険もありますので、なるべく広く損害を補填する保険に加入することが大切です。
【Q10】介護事業者の転倒事故にかかわる事業者の法的責任は、どのような場合に認められるのでしょうか。
(回答)ここでは、転倒事故の事例を、責任が認められた事例、認められなかった事例について具体的に説明します。
(1)転倒事故
介護事故のうち、もっとも多い事故であり、約6割を占めています。転倒事故は、あらゆる機会に発生する可能性のある避けがたい事故ではありますが、可能な限り対策を講じて事故を少なく、被害を軽くしなければなりません。高齢の入所者の転倒事故の態様は、施設内で歩行中にバランスを崩して(薬の副作用、廃用症候群による筋肉の衰え、施設内の設備の不備によるもの、例えば、滑りやすい床、わずかな段差、手すりがないなど)の転倒、ベッドにかかわる転倒、入浴時の転倒、車いすで移動中の転倒、トイレの便座から立ち上がったときの転倒、階段の昇降の際の転倒など様々です。
(2)判例の傾向
ア_転倒事故は、過失が比較的認められやすい事故態様です。判例は、専門性のある職業についている者について「高度の注意義務」を要求する傾向にあります。とくに、ショートステイやデイケアの場合は、利用者が比較的歩行ができること、長期入所の利用者と違って、職員と利用者、家族の関係ができていなかったり、利用者に関する情報が少ないために、事故が起こりやすく、過失が認められやすいのが現状です。
イ_転倒事故は、誤嚥と異なり、死亡に至る事例は少ないため、損害賠償金額は比較的低めです。しかし、骨折などにより、入院治療中、認知症が急に進行するとか、死亡することもあり、この場合、事故と死亡の因果関係があるとされれば、多額の損害を賠償しなければなりません。
(3)過失があるとして責任が認められた事例とその判断
ア_事例1(前橋地裁平成25年12月19日判決)
①_概要
利用者Aは、施設の入所前に入院していた病院で、ベッドの柵を乗り越えてしまったことから、入院中は、ベッドではなく、畳対応になっていた。
施設(介護老人保健施設)に入所する際は、Aの家族は、「病院では、畳対応になっていたから施設においても畳対応をしてほしい。」旨を施設に伝えていた。これを受けて施設も畳対応をとった。
しかし、Aが部屋で壁にぶつけたことがあったため、畳では立ち上がるときに、掴まるところがなく、かえって転倒しかねないとの判断で、畳からベッドに移した。ベッド対応にはしたものの、施設は、ベッドの下にマットを置くなどの対応はしていなかった。また、施設は、ベッドに変更したことを家族に知らせていない。
ベッドに移した後しばらくした夜、職員3名のうち、2名は別の入所者対応をしていた。残りの1名が、ベッドに正座していたAに声をかけようと近づいたところ、Aは足を動かしてバランスを崩し、ベッドヘッドと柵の間からすり抜けて床に落ち、その結果11ケ月後に急性硬膜下血腫により死亡した(この事例は、転倒事故とされていますが、転落事故ともいえるかと考えられます。)。
②_裁判所の判断
施設は、そもそも、畳対応からベッド対応にすべきではなかったこと、またベッド対応に変更した後には、転落転倒を防止するために、ベッドの柵の位置を工夫したり、ベッドの下にマットを敷くなどの安全措置をとらなかったこと、そもそも段差をなくすなどして、畳対応での不都合を除いたうえで、畳対応を継続すべきであったことから、施設に安全配慮義務違反があるとした。(損害賠償額は、総額約24,420,000円、死亡慰謝料を含む、その余の内訳不明)
イ_事例2(京都地裁平成24年7月11日判決)
①_概要
利用者A(82歳、女性、要介護度2、日常生活自立度ⅡA)は、施設(短期入所生活介護事業)入所契約の半年前から、腦梗塞になり左上下肢に麻痺が残っていたことから、ショートステイを利用するようになった。利用開始当初、Aは車いすを押して歩いたり、杖を使って歩くことができた。
しかし、ショートステイ利用開始から3ケ月後、Aは、深夜、ベッドから起床しようとして、バランスを崩して転倒し、その際ベッドの物置台に頭部をぶつけてしまった(本人の説明による。)。このときは、イソジンを塗布し、頭部を冷やし、午前中に外科医に診断を受けたが、大事に至らなかった。事故を受けて施設は、Aがベッドからひとりで立ち上がったときに転倒の危険があるとして、ベッドのキャスターロックをし、Aに、お手洗いに行くときは、ナースコールを押して、連絡するように念入りに伝え、ボタンを容易に押せるように工夫し、周囲に何もなければ、立ち上がる必要もないとの判断で、周囲の物置台と室内の簡易トイレを撤去し、さらに車椅子に自ら乗ろうとする意欲を持たせないために、従前ベッド横に置いてあった車椅子をベッドからもっとも離れた場所に移動した。また、1時間ごとに看視をしていた。その後いったん、退所し、再入所の3日後の午前0時ころ、巡視中の職員が、Aが車椅子のそばで、ベッドに足を向けて右側臥位で転倒しているのを発見した。Aは、右鼻翼に擦過傷、微量の出血、多量の軟便を失禁していた。ベッドから車椅子までの距離は、1.5ないし2メートルであった。
Aは、ベッドに戻され、入眠したが、午前4時半ころ、ナースコールがあり、駆け付けた職員は吐瀉物を認め、Aには意識状態の悪化が認められたことから、午前6時頃に救急車を呼び、総合病院に搬送されたが、12日後に急性硬膜下血腫により死亡した。
②_裁判所の判断
利用者Aの転倒の危険性は、死亡事故の頃には、具体化したものとなっていたし、施設は、転倒を防止する高度の注意義務を負っていた。施設は、前回事故後、移動する際にはナースコールをするように念入りに指示し、この事故の際には、午後10時、11時にAの様子を見てはいるが、これらの方策だけでは、事故を防げないことはこの事故が起こったことが如実に示している。Aは、ナースコールを押すという指示に従わない性向(認知症の影響とも考えられる)からして、単なる指示では、不十分であり、施設はAのような事故を防ぐためには、すでに取られた措置のほかに、Aがベッドから離れようとしたことを感知する離床センサーを設置し、夜間は、衝撃吸収マットをベッドから一定の範囲内に敷き詰める必要があった。以上の方策を併用することにより、このような事故を防ぐことが可能となるのであって、それでもなお、事故の防止が不可能であれば、契約にあるように「利用者の心身の状態が著しく悪化し、施設での適切な生活介護サービスの提供を超えるとき」に該当するとして、契約の解約の手段をとるほかはない。
③_損害賠償金額(合計金34,020,312円)
_逸出利益:7,493,432円
_死亡慰謝料:22,000,000円
_治療費:26,880円
_葬儀費用:1,500,000円
_弁護士費用:3,000,000円
ウ_事例3(東京地裁平成24年3月28日判決)
①_概要
入所者A(80歳、女性)は、以前から骨粗鬆症があり、またパーキンソン病、めまい、抑うつ状態の診断を受けていた。次第に歩行も困難になったので、施設に入所した。はじめは、一般病棟に入り、そのころは、杖を使いつつ、よろけながらも、一人で歩行はかろうじてできていた。なお、Aに関して以前通院等していた病院からパーキンソン病(重症分類3)、うつ症状を伴うとの情報提供を施設は受け取っている。
入所後、Aは施設内でも多様な態様で何回も転倒したが、負傷はしていなかった。施設としては、Aをナースステーション近くに置いたり、コールマットを敷いたり、ベッドに支援バーを設置し、転倒を防ぐ措置をした。さらに施設は、Aを認知症専門の3階のベッドに移した。施設職員は、Aの動静に注意し、転倒した日の夜中にも6回(最後は、午前5時)、Aが就寝していることを確認した。
午前5時30分ころ、尿意を訴えたため、Aを車いすで、トイレに連れて行き、排尿の介助をした。その際Aから、「わたし、転んじゃったの。」と言われた。Aは、下肢痛、頭部疼痛を訴えた。施設は、事の次第を家族に連絡し、病院に連れて行ってほしい旨を伝え、同日の午後4時過ぎに、家族がAを病院に搬送した。その病院で、Aは、大腿骨転子部骨折と診断された。なお、骨折を招いた転倒の正確な時刻や、態様は不詳である。
② 裁判所の判断
施設は、Aが入所後にも多数回転倒しており、転倒の危険性が高いことをよく知っていたのであるから、契約上の安全配慮義務の一内容として、Aがベッドから立ち上がる際などに転倒することのないように見守り、Aが転倒する危険のある行動に出た場合には、その転倒を回避する措置を講ずる義務を負っていた。
しかるに、施設はAが転倒した日の未明、Aがベッドから立ち上がり転倒する危険のある何らかの行動(たとえば、ベッドから出て行動する等)に出たのに、Aの動静への見守りが不足したため(仮に職員による見守りの空白時間帯に起きたとすれば、空白時間に対応する措置の不足のため)これに気づかず、転倒回避の適切な措置を講ずることを怠ったために、転倒事故が発生したというべきである。そうすると、施設は転倒回避義務に違反しており、契約上の債務不履行責任を負う。
③_損害賠償金額(合計金2,077,868円)
_治療費:520,590円
_近親者の看護介助費用:52,165円
_諸雑費:5,113円
_入通院慰謝料:1,500,000円
(4)施設に過失がないとされた事例
ア_事例4(東京地裁平成28年8月23日判決)
①_概要
A(87歳、女性、要介護度1)は、平成26年2月26日、株式会社介護付き老人ホームに入所した。入所前、長男夫婦と同居して、介護を受け、訪問看護を受けていた。しかし、Aには、左膝関節症、右足関節症、外反母趾等の身体症状や認知症があり、転倒や、よろめいてけがをしたこともあった。介護をしていた長男の妻の体調不良もあって、この施設に入所した経緯がある。
同年5月12日午後1時ころ、Aは、施設4階リビングで椅子から立ち上がろうとして、転倒した。事故当時リビングには、職員2名がいたが、リビングで食事をしていた入居者のうち、歩行に介助が必要な者をそれぞれの居室に移動させていた。
職員は、午後1時ころ、リビングから「ドスン」と音がしたことから、ただちにリビングに向かったところ、Aが床に倒れているのを発見した。Aは、「トイレに行こうとして立ち上がったところ、足を滑らせて転んだ。」と言った。左大腿部の痛みと脱力感を訴え、立てなかったところから、Aを病院に搬送し、検査をしたところ、左大腿骨転子部骨折と判明し、28日間入院、さらに退院してから6月9日から翌年2月22日まで通院した(全治療日数11日)。Aは、転倒事故後、平成26年6月30日、要介護度3と認定された。
②_裁判所の判断
Aは、転倒事故当時87歳であり、自宅で生活していた平成25年6月頃には、転倒して顔面を強打し、病院に運ばれたことや、2年ほど前にも自宅で起き上がった際によろけて、ガラスにぶつかり、11針縫うけがをした出来事があり、この転倒事故当時、脳血管性認知症と診断されていたが、失禁衣類をしまってしまうことや、帰宅願望あるほかは、会話による意思疎通は可能であり、施設において、個室で日常的な起居を行い、食事、排泄、衣服の着脱等も自立で行っており、運動等レクリエーション、食事、排泄のために移動場面においても、一人で歩行していたことが認められる。
また、医師作成の居宅療養管理指導には、平成26年5月に至り、転倒に留意すべき旨の記載がなされているものの、その根拠となる具体的な事実の記載はなく、施設職員の観察及びその分析、情報共有の結果によるも、Aの問題としては、失禁時の対応や帰宅願望への対応が中心であり、歩行能力については、格別具体的な問題は観察されず、入所契約等の締結後、施設においてAが転倒した事実はないほか、入所オリエンテーション時及びその後の連絡や面会の機会において、Aの家族から、転倒に対する具体的な不安は聞かれていない。
また、この転倒事故が発生したのは、Aの帰宅願望が高まり、施設内で徘徊していたなどの機会ではなく、昼食後、他の入居者と雑談して比較的落ち着いて過ごしていた時間帯に、職員が他の介助が必要な利用者を居室に送り届けていた際に、Aがトイレに移動しようとして、発生したものである。
以上の事実によれば、職員において、この転倒事故を具体的に予見することは、困難であったと認められ、この転倒事故は、施設の安全配慮義務に違反によって生じたものとは言えない。したがって、Aの債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求はいずれも理由がない。(なお、東京地裁の別の裁判体で同じ日付で、介護転倒事故について、施設の過失がないとした判決があります。この判決では、施設職員が終始見守るのは、その事例では不可能で、それを要求すると、かえって利用者の拘束を招ねきかねないとの指摘があり、参考になります。)
(5)判例の概観
裁判所の判断は、介護関係者にとっては、酷な判断と思う事例もあるかもしれませんが、特別な専門性を持つ介護施設に対して、「高度の注意義務」が要求されているのが、他の分野においても、判例の流れといえますし、それは介護関係者の専門性に対する国民の期待が大きいからでもあるわけです。
利用者がトイレのそばまで、職員に付き添われながら、トイレの中に職員が入って介助することを拒み、中からカギをかけ、トイレの中で転倒した事故について、それでもなお、職員は、利用者に対して説得を粘り強くするなどする責務があるなどとして、施設の責任を認めています(もちろん、利用者の過失も認めています。)。
また、事故(大腿骨頸部骨折)の発生から医師に診せる時間が半日以上もあって、事故の過失は認めなかったものの、その間放置されたことについて、肉体的、精神的苦痛を受けたとした、20万円の慰謝料を認めた事例もあります。
事例4は、施設の責任を否定したやや珍しい事例です。医師から「転倒に留意」との申し送りにも、具体的な根拠が記載されていないとし、そうなると、現場での具体的な対応は困難ですし、もし、具体的に、「立ち上がり時に転倒しやすい」との記載であれば、それなりの対応はできる可能性があり得ます。こまかく、具体的に利用者に配慮した介護計画を立てると、かえって、事故後に責任を追及されやすくなるのでは、との心配もあり得ましょうが、施設は保険があれば、通常は保険で補填できますし、なによりも、具体的に事故の予見可能性に気づき、配慮することによって、事故を防げる可能性は高まることでしょう。
(6)転倒事故について裁判所の判断に影響を与えた主な事情
ア_施設の廊下等の構造に少しでも段差(とくに2センチ以上)があったか。畳のへり、カーペット、絨毯等の敷物、電気コード等躓きやすい状態になっていたか。
イ_施設の各所に必要な手すりが十分備えられていたか。
ウ_施設の廊下、トイレ等に滑りやすいところはなかったか。
エ_利用者に、転倒を起こしやすい傾向があることを家族や病院から、正確に事前に把握し、職員に周知させていたか。
オ_利用者にその心身の特徴に応じて、介護につき、歩行の付添い等適切な配慮をしていたか。
カ_入所者の事情に応じて、ベッドの種類、高さ、位置に配慮していたか、転倒落下を和らげる措置をとっていたか。
キ_職員の付き添い、見回り、監視が、痔のある入所者に対応して、十分に行われていたか。
ク_以前に軽い転倒事故があった入所者に対して、再度の事故を防ぐ措置を検討し、再発防止策を十分かつ具体的にとっていたか。
ケ_事故後の対応は適切であったか。迅速な医療機関への搬送、家族への連絡など。
【Q11】介護事業者の誤嚥事故にかかわる事業者の法的責任は、どのような場合に認められるのでしょうか。
(回答)ここでは、誤嚥事故について、施設の責任が認められた事例と、否定された事例を説明します。
(1)誤嚥事故
誤嚥事故は、転倒・転落事故についで多い事故です。高齢者は、飲込み反射や飲み込む力が衰えていて、食事中に食べ物を喉に詰まらせて、気道をふさがれて窒息死するか、重大な後遺症をきたすこと、食べ物が気道に入り込み(高齢者は、咳などにより気道から異物を排出する機能が衰えている。)、気道から肺に入り、肺炎を起こして、時には死亡する事故のことです。
(2)判例の傾向
転倒事故に比較して、誤嚥の事例では、施設に責任がないと判断される事例は、割合多いのですが、死亡に至るか、重い後遺症を残すこともあり、施設の責任が認められると、賠償金額は、相当多額になります。
(3)施設の過失が認められた事例
ア_事例1(水戸地裁平成23年6月18日判決)
①_概要
利用者Aは、施設(介護老人保健施設)に入所する3年前からパーキンソン病の症状が進み、通常食は摂れない状態になり、お粥とペースト状にしたおかずを食べていた。Aの症状が進行したこともあって、Aは施設に入所した。その際施設に対して、病院からAに関して、「食事摂取・自立」、「手の震え(+)、食べこぼし(+)」「食事内容・全粥きざみ食」との申し送りがあった。
家族からも「全粥きざみ食」の希望があり、施設は、その希望に沿って食事内容のサービス計画を立てていた。しかし、入所後Aの食事摂取が予想外に良好であり、「刺身を常食で食べたい。」とのAからの希望あったことから、Aの家族に連絡しないで、刺身を常食で提供するようになった。しかし、しばらくしてから、ある日Aを職員の目の届くところに座らせ、はまち、まぐろの刺身(2.5センチ、4センチ、0.5センチ)を食べさせていたところ、Aは突然刺身を喉に詰まらせ窒息状態になって心肺停止状態になり、当該施設の経営する隣接の病院で蘇生措置を受けたが、意識が回復しないまま、4ケ月後に死亡した。
②_裁判所の判断
Aの嚥下状態は、とうてい良好とは評価し難い状態であったもので、Aには、誤嚥の危険性があったものと認められるところ、継続的にAの介護にあたっていた医師、職員は、これを認識していたか、容易に認識できはずである。提供された刺身は、健常人が食べるのとそれほど異ならない大きさであって、Aが嚥下しやすくするための工夫を特段講じたとは認められない。まぐろは、筋がある場合には、咀嚼しづらく噛み切れないこともあるため、嚥下能力の劣る高齢者に提供するのに適した食物とはいい難く、職員はAの嚥下能力の低下、誤嚥の危険性に照らせば、Aに対して刺身を提供すれば、誤嚥する危険性が高いことを十分予想し得た。施設が、刺身を常食として提供したことは、介護契約上の安全配慮義務違反、過失が認められるとして施設の責任を認めた。
③_損害賠償金額(全額 金22,035,682円)
_付添い看護費:670,000円
_葬祭費用:1,500,000円
_死亡慰謝料:15,000,000円
_逸出利益(年金):2,855,682円
_弁護士費用:2,010,000円
イ_事例2(大阪高等平成25年5月22日判決)
①_概要
利用者A(85歳、女性)は、ある病院で、潰瘍性直腸に関して手術を受け、退院までずっと粥食が提供されていた。退院後は、被告である施設(株式会社介護付有料老人ホーム)の個室に入居した。入居に際し、施設は病院から、「食道裂孔ヘルニアにより、ときおり嘔吐を認める。誤嚥がなければ、経過観察でよいと思う。」との引継ぎがあった。施設は、診療情報提供書から、Aには、「難治性逆流性食道炎、食道裂孔ヘルニア」の既往症があること、食後の嘔吐があったとの情報を得ていた。Aは、施設に入居してから、誤嚥事故までに、4回食事をしたが、誤嚥をうかがわせるような症状はみられなかった。事故当日、施設は、ロールパンを含む朝食をAの個室に配膳した。Aは、一人で朝食をとっていたが、ロールパンを誤嚥して、昏睡状態になっているところを発見され(配膳20分後)、約2時間10分後、救急車で病院に搬送されたが、その日の午後7時ころ死亡した。
②_裁判所の判断(施設の過失を認めなかった地裁判決に対する高裁判決、請求認容)
施設は、診療情報提供書、看護サマリー、紹介状などから、Aに難治性逆流性食道炎等の既往症があることを知っており、これらの記載により、Aについて誤嚥が危惧されるとの意味内容を感得することは、医療の専門家でない読み手であっても困難なことではない。高齢者の事故で、転倒と誤嚥が多いことは、周知の事実であるところ、高齢者を扱う介護事業者のスタッフは、病院からの書面により、その意味内容からして、Aに対し通常の入所者に比して誤嚥について特に注意が必要であることを把握できないはずがない。とりわけ、介護施設に入所する者にとっては、環境が変化すれば、心身に負担が増すことになるのであるから、持病がどのように表れるか注意深く観察する必要があり、医療機関の初回の診察・指示があるまでの間は、Aの誤嚥防止に意を尽くすべき注意義務があったというべきである。本件においては、Aを居室において食事をさせ、Aに異常が生じても、気づきにくいという事情があったのであるから、このような状況においては、食事中の見守りを頻回にし、ナースコールの手元配置等を講じるなどして誤嚥に対処すべき注意義務があったというべきである。
しかるに、施設は、Aの既往症や紹介状の記載に顧慮することなく、居室で食事をさせたにもかかわらず、ナースコールをAの手元に置くことなく、見回りについても配膳後約20分も放置していたのであるから、誤嚥が起こっても発見できる状況になかったとはいえ、Aの誤嚥防止に対する適切な措置が講じられたということはできず、Aの身体に対する安全配慮を欠いた過失がある。
施設は、原則として食堂で食事を提供すると利用者側に説明したにもかかわらず、Aと家族が個室での食事を希望したので、希望に配慮して個室での食事にしたので、Aにも過失があるから、過失相殺(Aにも、事故の責任の一半があるので、損害額を減らしてほしいとの主張)を主張したが、認められなかった。しかし、慰謝料の金額において斟酌した。
③_損害賠償金額(全額 金15,438,620円)
_死亡慰謝料:10,000,000円
_相続人固有慰謝料:2,500,000円
_入院費用:17,190円
_葬祭関係費:1,566,430円
_弁護士費用:1,400,000円
(4)過失が認められなかった事例
責任がないとされた事例は、転倒事故に比べて多いのですが、敢えて、責任を認められなかった事例は、一つにとどめました。
ア_事例3(神戸地裁平成16年4月15日判決)
①_概要
特別養護老人ホームにおいて、入所者A(83歳、男性、うつ病、老人性認知症、白内障により全盲)は、介護職員の介護を受けつつ、午前7時40分ころから、朝食をとっていたところ、パン粥を詰まらせて、窒息により死亡した。
当日は、四角のテーブルの長辺にAが車椅子で位置し、短辺には他の入所者が座り、両名の間のテーブルの角に職員が座って、2名の介助をしていた。
食事中のAの姿勢は、リクライニングの背もたれは、60度に起こし、枕を後頭部にあてて、前屈状態であった。職員は自分の左手にいるAに、はじめは牛乳を2口吸い飲みで介助し、パンを小さく一口大にちぎって口に入れたが、せき込んでパンを吐き出した。そこで、ヨーグルトを2ないし3口をスプーンで介助した。2口目から口に溜めている時間が長かった。副食のレタス、ベーコン炒めは、一口食べてむせたので、以後介助しなかった。
当日、Aは、よくむせるので、職員はパン粥をスプーンで一口介助したが、なかなか飲み込めず、しばらく口に溜めていたが、飲み込むように促すとようやく飲み込んだ。その後職員は、隣の他の入所者の介助をしながら、Aの様子を観察していたが、むせたり、咳き込んだりすることはなかった。
職員は、いったん席を立って下膳の手伝いをし、午前8時5分ころAに対して再び食事介助を始めた。再開後、職員は、Aに再びパン粥を一口介助したが、口を開けようとしないので、隣の他の入所者を介助していたところ、8時8分ころ、急にAが「ヒーヒー」と言いはじめ、顔面蒼白となった。
職員は、Aを前傾させて、背中を叩いたが、変わりがなく、医務室にAを運び、看護師が吸引器により、吸引を開始したところ、パンらしきものが少量吸引できた。その後も別の方法で吸引をしたが、効果がなく、その後Aを車椅子から降ろし、看護師がアンビュウーバックでの吸引をし、心臓マッサージをしたところ、Aは、いったん自発呼吸をしたが、すぐに停止した。8時25分頃、医師がかけつけたが、すでに瞳孔が散大し、反応もないようであったので、病院の救急室に搬送し、搬送中及び救急室で心肺蘇生措置を継続しつつ、挿管の準備をしたが、午前8時40分死亡と確認された。
②_裁判所の判断
誤嚥のメカニズムは、1.食物の認識、2.そしゃくと食塊の形成、3.咽頭への送り込み、4.咽頭通過、食道への送り込み、5.食堂通過の5段階から形成されるところ、職員としては、Aについて、本件事故において、5の段階の誤嚥の兆候は認識していないのであるから、Aが介助したパン粥を、なかなか飲み込まないという事態を受けて、Aに誤嚥の可能性があったと認識することは、不可能であり、仮に認識すべき義務があるとすると、これには、食事中は、常に肺か頸部の呼吸音を聞く必要があり(ただし、正確に聞くには、熟練が必要である)、また、誤嚥をいちばん正確に評価するには、嚥下造影が必要であり、このような義務を特別養護老人ホームの職員に要求することはできない、としてAの家族の請求を棄却した。なお、Aは、うつ病の薬を服用していて、副作用として、嚥下困難、のどの渇きが生じるから、施設はその点でも、高度な注意義務を負っているとの主張には、Aには服薬による悪性症候群は生じていず、そのために嚥下困難、渇きは生じていなかったから、過失の判断には影響がないとした。
(5)嚥下事故について裁判所の判断に影響を与えた主な事情
ア_嚥下しにくい食材が提供されたのか。
イ_嚥下しにくい、または、喉に詰まりにくい大きさ、形状の食材が提供されたか。
ウ_嚥下障害の兆候あるいは既往のある利用者に対して、特に注意し、介添えをしつつ、援助し、一匙づつゆっくりと無事に飲み込むことを確認してから、次の一匙を食べさせたか。
エ_細かく刻んだり、柔らかくしたり、とろみをつけるなど、嚥下しやすい工夫を利用者ごとに工夫していたか。
オ_病院、家族からの引継ぎなどの、利用者の誤嚥に関する情報があったときには、職員にその情報を共有させ、適切な対応をとっていたのか。
カ_事故後に迅速かつ適切な対応をとったか。また、速やかに家族へ連絡したか。
(6)判例の概観
事例1、事例2では、食材、大きさについての過失があるとされましたが、高齢者にとっては、咀嚼しにくい、飲み込みしにくい食材は、細かく刻んで、とろみをつけるなど、飲み込みやすいように工夫することが必要です。また、時間がかかるのですが、ゆっくりと無事に飲み込んだことを確認してから、一匙づつ介助することも大切です。特に餅は、のどに詰まらせやすいとされているので、食材の選択には注意しなければなりません。食材の大きさについて、通所介護の事例ですが、その事故の前に、別の通所介護事業者が担当していた折り、肉を食べて、のどに詰まらせ顔面蒼白になったことがあり、以前の通所先から家族にそのことを連絡してありましたが、家族、以前の通所先からは、事故が起きた事業者にはその旨の連絡がされていませんでした。被告の事業者所属のヘルパーが、介助するにあたって、冷蔵庫から、さつま揚げを出して、麺の上に切ることなく、そのままの形で提供したところ、さつま揚げを喉につまらせて、窒息し、翌日死亡した事例で、過失を認められた事例があります。
他方、事例3のように、誤嚥事故は、なかなか見分けにくい、気づきにくい面もあることもあって、施設の過失が否定される事例も、転倒転落事故に比べて多い傾向にあります。しかし、できる限り食事中又はその後の状態には、観察を怠らず、いささかの異常にも、気づくことと、直後からの適切な対応措置をとることが必要です。